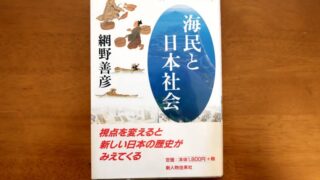 資料集
資料集 網野善彦『海民と日本社会』新人物往来社,1998年
網野善彦『海民と日本社会』新人物往来社,1998年網野善彦『海民と日本社会』新人物往来社,1998年上ノ国町勝山館の発掘例から、北海道を含む日本海沿岸地域における「唐人」や中国大陸との強い結び付きの可能性が指摘されている。この十三湊から大量...
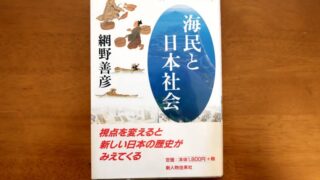 資料集
資料集  函館市
函館市  北斗市
北斗市 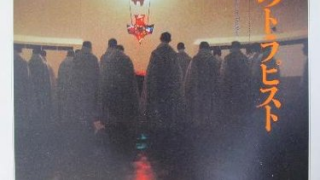 資料集
資料集 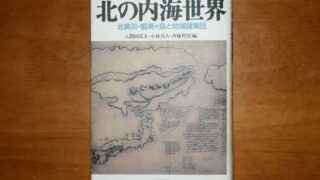 資料集
資料集  函館市
函館市  函館市
函館市  函館市
函館市  函館市
函館市  函館市
函館市